ワンオペ育児、乳がん闘病を乗り越えて。エンジニアにしはらちひろの「ダメもと精神」は次のステージへ
-
執筆 : 鈴木陸夫
- /
-
写真 : 藤原 慶
- /
-
編集 : 小池真幸
- /

CREと呼ばれる、顧客の信頼性を高めることを目的としたエンジニアリングの専門職があるのをご存知だろうか。Customer Reliability Engineeringの略で、顧客から寄せられる問い合わせや困りごとに対し、技術的なバックグラウンドをもってサポートしたり、製品やサービスの改善提案を行ったりする役割を担う。
2016年にGoogleが提唱したことで知られることになったCREだが、日本ではまだ確立しているとは言い難い。そんな領域を自らの進むべき道と見定め、仲間と共に、エンジニアキャリアの新たな可能性を切り拓こうと奮闘するのが、SmartHRのにしはらちひろさんだ。
にしはらさんがCREという情熱を注ぐ先を見つけるまでには、月並みな表現だが、紆余曲折の日々があった。ファーストキャリアはアパレル販売員。未経験でエンジニアに転身するも、ワンオペ育児との両立で一時は「詰み」寸前まで追い込まれた。現職に就いてからも、乳がんの発覚・闘病生活という大きな壁が彼女の行く手を遮った。
言わずもがな、人生において「選択」は重要だ。だが、そもそも選択肢があることを知らない場合、自分がやりたいことが見えていない場合、目の前のことに精一杯でそれ以外のことなんて考えられない場合……選択したくてもできない状況というのが、人生には存在する。
そのすべてを経験した上で今、にしはらさんが感じていることとはなんだろうか。
プロフィール
- にしはらちひろ株式会社SmartHR 技術統括本部 労務プロダクト開発本部 CRE部
短期大学卒業後、アパレル業界に就職。アニメーションスタジオの総務などを経験した後エンジニアに転向。複数社でエンジニアとしての経験を経て、2019年にSmartHRへ入社。プロダクトエンジニアとして基本機能と呼ばれる部分の機能開発に携わる。2025年7月より、新たに立ち上がったCRE(Customer Reliability Engineering)部に所属。2人の子供を子育て中。
情熱を注ぐ対象としてのCRE
現在の所属は「CREユニット」とありますね。事前に拝見した「Women Developers Summit 2024」での発表スライドの時点ではまだ部署にはなっていなかったと思うんですけど、その後、正式に発足したということでしょうか。
そうなんです! 弊社はちょうど7月から下期に入るんですが、その期が切り替わるタイミングでCRE部CREユニットというものが爆誕しまして。そこに所属することになりました。
にしはらさんの思いの込められた活動、ということですよね?
そうですね。CREという言葉を知り、やりたいと思って動き出してから、もう1年くらい。社外の方にインタビューさせていただくなど情報収集することから始めて、ようやくユニットとして立ち上がったかたちです。
私を含めてまだ二人しかいないので、地道に一つひとつ進めているような状況なんですけど。私がメンバーで、もう一人がチーフ。その方は実は、1年前に「社外のCREの方」としてインタビューさせてもらった人なんですよ。その後、ご縁あってSmartHRに来ていただけることになって。
ご自身で口説かれたわけですか。
そういうことになりますかね。その方が当時、SNSで転職匂わせ的な投稿をされていたので、ダメもとで声をかけたら、「ぜひお話を聞かせてください」と言っていただけて。


生来の「ダメもと精神」で未経験からエンジニアに
エンジニアの仕事を始めたのはいつごろですか?
23歳のときなので、もう20年近く前になりますね。
その前はまったく違うお仕事をされていたと伺っていますが、どういう経緯でエンジニアに?
短大を卒業したあと、半年ほどアパレルで働いていたんですけど、2000年代前半なので、アパレル業界もなかなかハードな働き方をする状況にあって。ちょっと体を壊してしまったんです。
それで自分のペースでゆっくり働ける仕事、なおかつ、やっぱり自分の好きなことをしたいという思いもあり、駅に置いてある求人雑誌をめくる中でたまたま見つけたのがアニメーションスタジオの総務の仕事でした。当時住んでいた家から近かったし、もともとアニメやゲームが好きだったので、「ちょっといいかも」と思って、そのスタジオに入ることになりました。
私の仕事は総務だったんですが、当時は今のようにクラウドが主流ではなかったので、画像や動画のデータは全部、オンプレでスタジオに持つような時代で。そういうデータを管理している、今で言う情シス的な役割をされている方がいらっしゃったんです。私は高校生の頃から個人サイトを作っていたりして、割とそういうことが好きだったので、その方とちょいちょいお話をさせていただく機会がありました。
その時点ではエンジニアになろうなんてまったく思ってなかったんですけど、働いているうちに徐々に体調も戻ってきて、だんだんと先のことを考えるようになって。仕事は引き続き楽しかったんですが、このままアニメ業界で総務として働くのは、自分のキャリアとしてはどうなんだろう、って。

現在に関してある程度余裕が出てくると未来について考え出して、逆にモヤモヤしてきてしまうことってありますよね。
で、そういう悩みがあることを相談したところ、その方は別の会社でエンジニアとして働いた経験もお持ちだったので、「エンジニアとか、どう?」と勧めてくださって。
当時はITバブルのような時期で、本当に誰でもエンジニアになれたというか、私のように未経験でもとってくれる会社がたくさん求人を出していたんです。そこでダメもとで……あ、私はダメもと精神でやってみることが本当に多いんですけど、家から無理なく通えそうで、未経験にもそれなりに手厚そうなところを自分なりに調べて、試しに受けてみるかという感じで面接を受けに行きました。
本当に受けさえすれば入れるみたいな時代、なんなら受けるだけでQUOカードがもらえるような時代だったので、その場で「じゃあ、いつから来られますか?」みたいになって。「ああ、なれるんだ」と、エンジニアに切り替わった感じです。
個人サイトを持っていたというお話でしたけど、その時点でプログラミングに関する知識はどの程度お持ちだったんですか?
ほぼ何もわかっていなかったです。個人サイトをやっていたと言っても、当時はテキストサイト全盛の頃だったので、どこかのレンタルサーバーを借りて、プレーンなHTMLを書いていた、という程度で。
入社して最初はJavaをやったんですけど、3ヶ月間、会社のお金で研修を受けられる制度があって。その最後にSJC-Pの試験(かつてサン・マイクロシステムズが認定していたJavaプログラミングの資格試験)に合格しないと、試用期間で終わりになってしまう。「入社したあとに言うのはずるくない?」とは思ったんですけど、そこで初めてプログラミングというものに触れて。ああ、こうやるとこういうふうに動くのかというのをそこで初めて知った感じです。
ちなみにですけど、その「ダメもと精神」はどこからきているものなんでしょう?
自分はすごく小心者なので、一度考え出すといろいろと考えすぎてしまって、一歩も踏み出せなくなるところがあって。そういう自覚があるので、あえて考えないで「なるようになるだろう」「やらないで後悔するより、やって後悔する方がいいだろう」と思って、踏み出すように意識してきました。
アパレルのときも、あっちの方がいい会社だけど、こっちの方が入りやすそうだからという理由で選んで後悔したところがあったので、ダメもとでも、まずはやってみようとなっていったんだと思います。
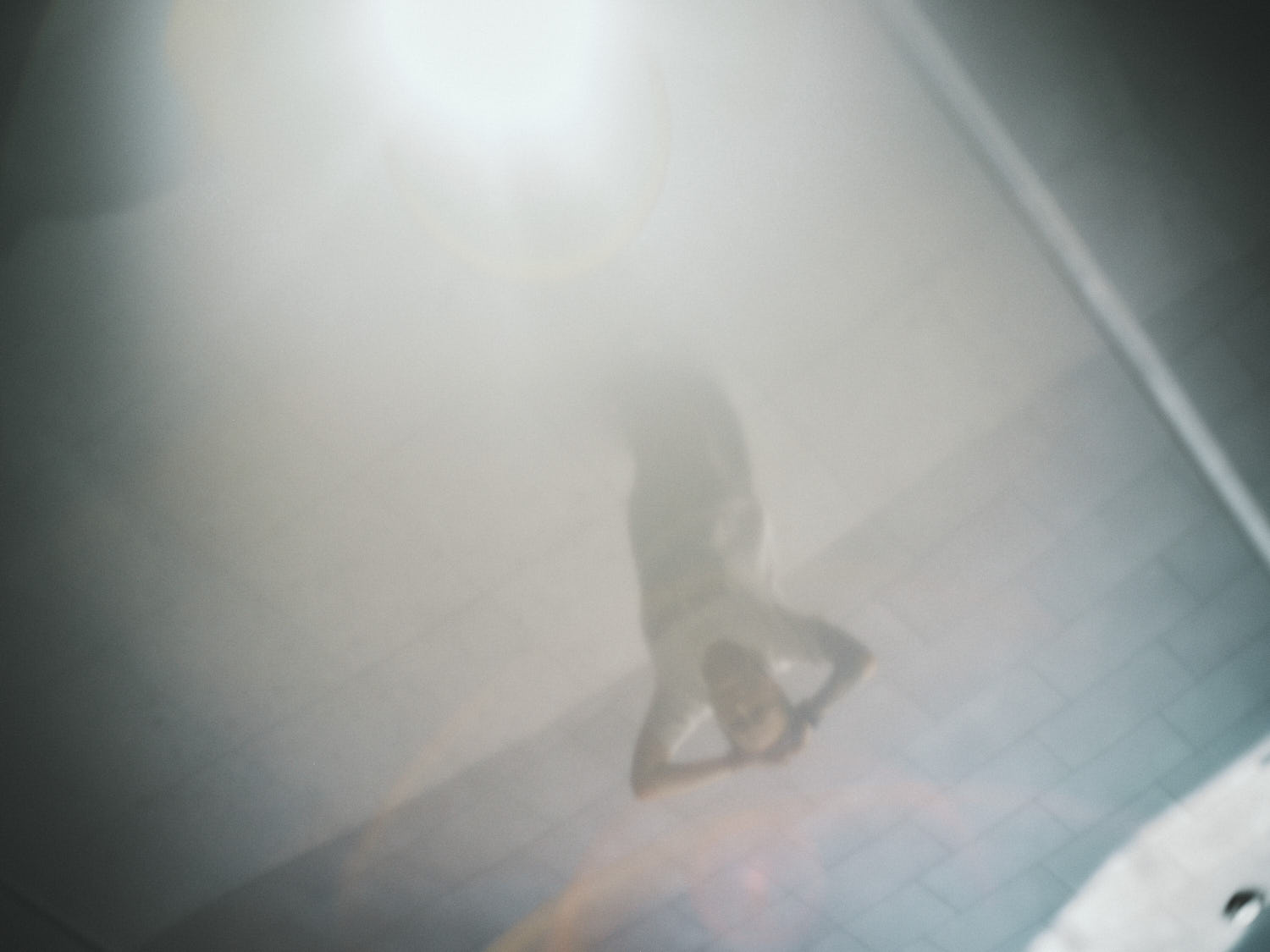
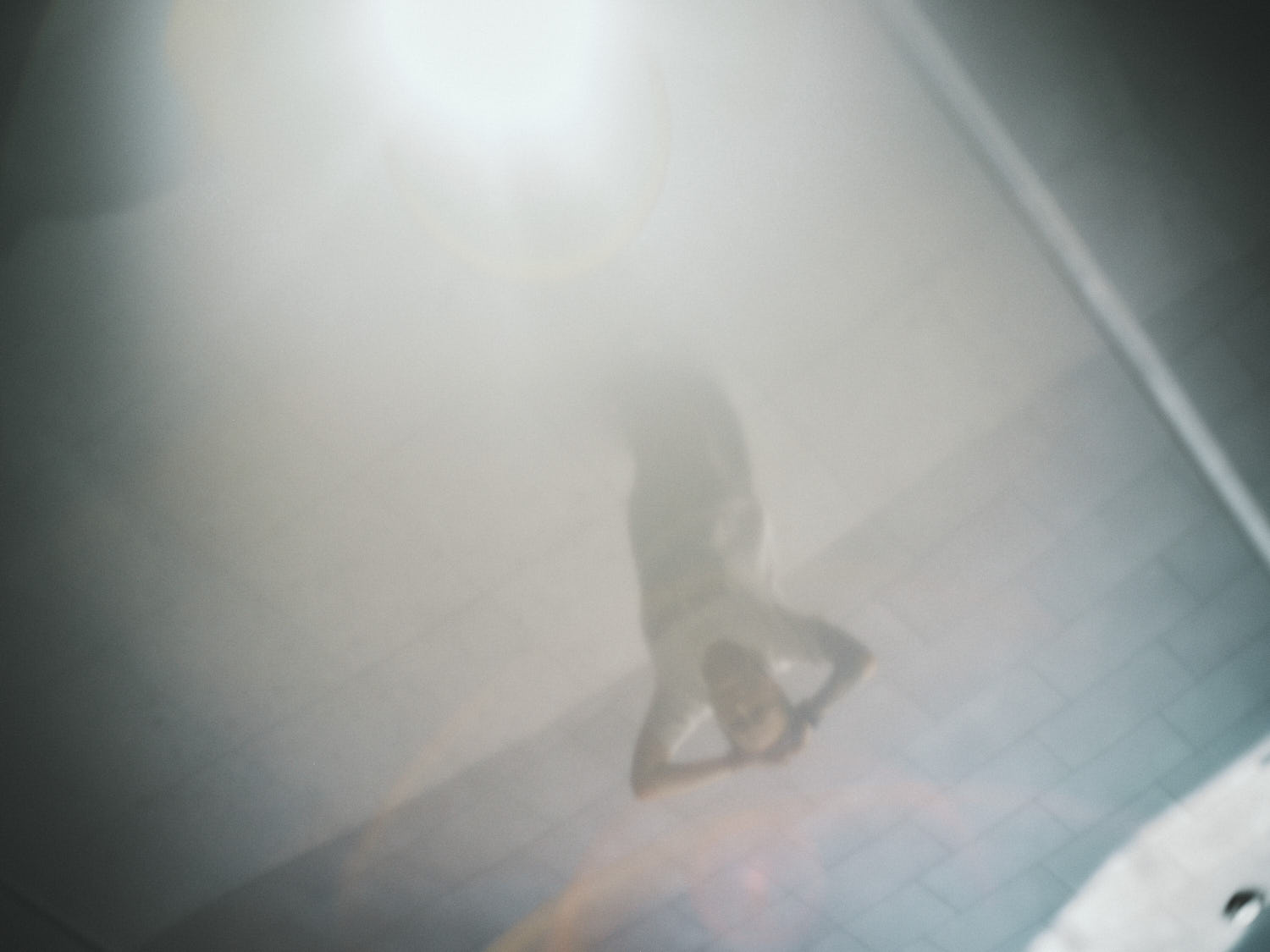
「1社目の選択」は誤りだったのか
そこでのお仕事はどのようなものだったんですか。
いわゆるSESの会社だったんですけど、最初の資格を取るまでは会社ではなく、銀座にある提携先の学校のようなところに通って、本当に毎日プログラミングの勉強をしていました。3ヶ月経って試験に合格して、合格証を持って本社へ行ったら、その日のうちに「じゃあ現場を探しましょう」となって。それで、受託開発の小さなベンチャー企業に派遣されて働き始めた、というのが始まりですね。
結構ハードな働き方だった?
今思うとハードだったかもしれないです。朝9時から夜の9時まで、毎日12時間ぐらい働いていましたから。ちゃんと電車に乗って帰れるし、当時は何も感じていなかったですけど、今振り返ると、結構働いていたなあと思います。
実際になってみたエンジニアはどうでしたか。
楽しかったですよ。悩むことももちろんあったし、落ち込むこともたくさんありましたけど、総じて楽しかった。わからないことがあったらわかるまで自分で調べればいいし、自分のペースでいろいろとできるのがいいなって。理不尽に怒られることもなかったですし。アパレル販売出身者からすると「座って仕事ができる!」「好きなときにお茶が飲める!」というだけで、もう。
でも、自身のブログには「1社目の選択を誤った」と書いていらっしゃいましたよね。これはどういうことだったんですか?
最初に派遣された現場には結局1年いたんですけど、自分は業界のことを何も知らずに入った人間なので、他の会社がどんなことをしているのかもわからないし、本当にもう、この会社で経験したことがすべてという感じで。一応1年間やって、Javaを書いたりRubyを書いたりもしていたし、ある程度のことはできるようになっているつもりでいたんです。そんなタイミングで、まだ立ち上がったばかりの別の現場に異動することになりました。
「Rubyができるから」という理由で呼ばれて入ったんですけど、1年もやってきた人ってことで、向こうの期待値も高めだったんでしょうね。入ってみたら「えっ、これできないの?」「あれもできないの?」とすごく言われて、自分としても「ああ、これを知っておかないとまずかったんだ」と思うことが本当に多かったんです。
そこで感じたギャップというのは、たとえばどんな?
前の職場ではそもそもターミナルをあまり使ってきていなかったので、「この開発環境を作っておいて」と言われても「どこで、どうやって書いたらいいんですか?」と聞くことになって、驚かれたり。インフラ面を見させてもらうこともほとんどなかったので、「こっちのサーバに入って」と言われてもピンとこない。その度に「どういうことですか?」と聞き返してしまう、とか。
ただ、ついてくれたメンターさんが非常にいい方だったので、すごく助けられました。「そんなことも知らないのはヤバい」「このままではマズいよ」って、すごく厳しく指摘されるんですけど、一方で本を貸してくださったり、休日にはずっとSkype越しに付き合って、朝までいろいろと教えていただいたりしました。
その現場には3ヶ月しかいなかったんですけど、その前の1年よりずっと濃い時間だったというか。エンジニアとしてどう振る舞うべきなのかといったことも、そこで教えてもらった気がします。


1社目ではいろいろとお膳立てされた上で、一部分だけを任されていた、だから起きてしまったギャップということでしょうか。
それもあったと思うんですけど、今思うと、会社として求められていたレベルもそこまで高くなかったのかなと。一体何をしていた1年だったのだろうと、いまだにちょっと不思議な感じがあって。
当時は何もわからないので、自分より長く現場にいる先輩にいろいろと質問させてもらっていたんですけど、あるとき「配列と連想配列の違いがわからないです」と聞いたら、「えっ、一緒じゃないの?」と答えが返ってきて。話は平行線のまま終わってしまったんですが、今思うと、そういう質問にちゃんとした答えが返ってこない時点で疑問を持つべきだったんでしょうね。
これはエンジニアに限らず、新卒入社した時点ではその会社が世界のすべてにならざるを得ないところがあると思うんですけど、いろいろな現場を経験できるSESは、そこから相対化していきやすい職種とも言えるのでは?
ああ、それはそうですね。3ヶ月の濃い時間を過ごさせてもらったあと、私が思ったのも、このままでは自分の経験を積むという点でヤバいんだろうなってことで。「その後の契約はどうする?」と聞かれたときも、もっと武者修行しないとダメなんだと思い、「申し訳ないですけど、いろいろな現場に行きたいので、最短の契約でお願いします」とお答えしました。
それからは、現場でわからないことが出てきたら自分で勉強して、できるようになったらまた次の現場へ行って、わからないことを勉強して、というのを繰り返しました。自分で言うのもなんですけど、私はビジュアルが当時から尖っていたので、会社からは「堅いところには行けない」「銀行とかは絶対に無理だ」と言われていて、だから配属先はベンチャーが多かったんですけど、その中でもできるだけいろいろなことに触れられる現場に行かせてもらえるよう、お願いしていました。
時短、給料半減、ワンオペ育児で心身はギリギリに
しかし出産・育児を経て、その状況が大きく変わってしまったんですよね。
そうなんです。長男を妊娠して産休・育休をとって、その間はもちろん普通に子育てに集中できたんですけど。子供が8ヶ月くらいのときに復職して、そこからは毎朝子供を保育園に送り届けてという、子育てあるあるの生活が始まりました。
夫とはアパレル時代に知り合って、エンジニアになった半年後くらいに結婚したんですけど、メディア関係の仕事をやっていて、すごく忙しくて。地方ロケに行くと、1ヶ月くらい家をあけてしまうことも普通にあって。その1ヶ月は自分しかいないので、本当に完全なるワンオペです。
お金の面でもだいぶ条件が悪くなってしまったとか。
保育園の送り迎えがあるから時短で働かなくてはならないので。その会社では子供を育てながら働く人が初めてだったのか、「時短で働く人を現場に入れるのは無理だから、うちの会社の事務でもやるか?」とか、今だったら信じられないような変な提案をいっぱいされて。
でも、私はエンジニアとして働きたい気持ちがあったから「給料が下がってでもいいから、現場に入れてください」とお願いしました。そうしたらそれまでの半分以下の給料に下がっちゃって。保育料だけでもそこそこの金額なので、まるで保育料のために働いているような状態になってしまったんです。
子供が熱を出したらお迎えに行かないといけないし、そこまで集中して仕事ができるわけでもない。帰ってきて子供の面倒を見るのも、あれこれやりながらになるから、ちゃんと向き合うことができない。全部が中途半端になって、ずっとモヤモヤしているみたいな感じ。「私は一体なんのために働いているのか」みたいな考えが、ずっと頭の中をぐるぐるとめぐっていました。


そうもなりますよね。
本当に毎日いやだなという気持ちで働いていたのを覚えてますね。このままだと続けられないな、しんどいな、今の現場の契約が一区切りついたらもう辞めよう、と思うところまで落ちていました。肉体的にも精神的にもギリギリのところだったんじゃないかと思う。
にしはらさんのその後のキャリアを知った上で聞いていると、そんな状況からよくぞここまで持ち直したものだな、と思ってしまうんですけど。
運が良かったと言えば良かったのかもしれないです。
当時の私は今以上にSNSを乱用する人で、何かあればすぐにつぶやいていたんです。疲れている中でも、唯一できたのがSNSでの発信だったから。行き帰りの電車の中とか、ちょっとした時間に「ああ、疲れたなあ」とか、思った気持ちを素直に書いていて。今振り返ると、当時はネガティブな投稿が相当多かったんじゃないかと思うんですけど、それを昔現場で一緒に働いたことがある人がたまたま見ていてくれていて。
GMOと一緒になる前の、くまポンのシステム開発を請け負う会社の人だったんですけど、「もう本当に無理!」と思っていたタイミングで、「ちょうどサービスを立ち上げたばかりで、猫の手も借りたい状態だから、時短でもいいから来てほしい」って誘ってくれて。
ありがたいですね。
残業もできないし、子供が熱を出したらお迎えに行かないといけないし、とてもじゃないけど100%で働ける状況ではないですよって、期待値を低く持ってもらいたくて、自分の状況をすべて包み隠さず伝えたんですけど、「それでもいいから来てください」と言っていただけたので。その人に誘ってもらえていなかったら、私はおそらく今、ここにはいないだろうと思います。
ブログでにしはらさんが置かれた状況を読んで、改めて思わされたんですよね。LIFE DRAFTは「選択」のメディアを謳っているけれど、選択できるのはある程度余裕がある状況での話なんだな、本当に余裕のない状況では、仮に選択肢があったとしても、そもそもそういう発想には至らないんだなって。
今振り返れば、ネットでいろいろな企業のサイトを見て、求人を探せば良かったと思うんですけどね。当時は精神的にも肉体的にも疲れきっていたので、自発的に動くということが本当にできなかった。仕事に行って、保育園に行って、子供を連れて帰って、ご飯を食べさせるだけ。その日常をやりくりするだけでいっぱいいっぱいのような感じでしたから。

立ち上がるエンジニアとしての自意識
転職してその状況はだいぶ改善されたわけですか。
ワンオペはもちろんずっと続くんですけど、働く環境としてはすごく改善されました。社長さんをはじめ、お子さんをお持ちの方が多い会社だったので、子育てへの理解があって。「子供が熱を出してお迎えの電話が来てしまった」と言うと「すぐに行ってあげて」と言ってもらえたり、退勤時刻の前でも「キリが良ければ早めに上がっていいよ」と言ってもらえたり。
現場にいるエンジニアの方もすごくいい方が多かったし、仕事をしていて楽しかったです。
エンジニアとしての成長欲求を満たすこともできた?
これもあるあるですけど、SESである程度働いていると、自社サービスをやりたい気持ちになるんですよね。そういう会社に転職できたことには「やった!」という気持ちがありました。
現場には常にいろいろな技術の情報が飛び交っていて、活発に勉強会に参加するメンバーも多かったので、自分は参加できなくても、翌日に内容を聞くことができた。そういう形で引き続き勉強していくことができました。
そうやって環境が整っていくと、自分でももっと勉強会やコミュニティに顔を出したいという、エンジニアとしての欲が出てくるのでは?
めちゃくちゃ出てきましたね。勉強会の話を聞くと、やっぱりすごく楽しそうなので。もちろん子供を置いてはいけないから、毎回は無理ですけど、これだというものには親の力を借りて参加することなんかも考え始めました。
この会社ではかなり長く働かれているんですよね。
そうなんです。時短だし、最初は「簡単なことをやる人」というテイで入社したんですけど。途中で社長さんに「思ったよりできるから開発にも入ってほしい」と言われて、そこからはお手伝いだけでなく、本格的な開発に入れてもらえるようになりました。働きやすかったし、気づいたら7年ぐらい経っていましたね。最終的には一番の古株になってました。


そこから転職したのは?
途中で産休・育休をもらって2人目を産んで、「また心機一転やるぞ」と思って復職したんですけど、休んでいる間に、昔からやっていたメンバーがどんどん会社を離れていくということが起きて。
自分のいた開発会社とGMOくまポン本体が一緒になったことで、お世話になっていた社長も一線を退いたりもして、開発チームの雰囲気や体質が変わりつつありました。言い方が難しいんですけど、それまであった働きやすさのようなものが少しずつ失われていく気配があったというか。おそらくそれをいち早く察したメンバーから抜けていったんだと思います。
古くからの仕様を知っている人がいなくなるたびに、古株である私の負担も少しずつ大きくなっていって。子供を産んで復帰したばかりだったし、このまま行くのは怖いかもしれないという気持ちが芽生えてきた。それで「もう7年もいるし、他のところも見てみよう」「ダメだったら今のところでそのまま働けばいいだけだから」と思って、転職に向けた情報収集を始めました。
そうして選んだ転職先が、SES時代に縁のあった企業だった。
その企業の方とは、一年に一回は飲み会をやるくらいには仲が良くって。「転職を考えている」「いいところがあったら行きたいと思っている」みたいな話をしたら、「良かったらうちも候補に入れてよ」と言ってもらえて。
ちなみに、そのときにはSmartHRも候補に入っていたんですよ。せっかく転職するなら一番合うところを選びたいと思って、時間の許す限りカジュアル面談をして、いろいろとお話を聞かせてもらっていました。
SmartHRからも「ぜひ来てください」と言われて、すごく悩んだんですけど、その当時はまだ子育てしながら働くことへの恐怖心が拭えなくて。SES時代に経験した企業であれば、一緒に働いたことのある人がいるし、自分の事情もわかってもらえている安心感があったので、そっちを選んだ感じです。
エンジニアとしてのやりたいことより、自分の中でイメージが持てることを優先した選択だった?
そうですね。そのときはまだ2人目が手のかかる時期だったこともあって、完全に自分の「楽しそう」という気持ちにだけ従って決断しても、その先でどうなるかはわからないし、何かあったときに怖いな、と。「安パイを選んだ」というと表現が悪いですけど、それが自分の中の落としどころだったんだと思います。
チームで働きたい、という欲求
しかし、1年後にはSmartHRへ転職するわけですよね。
前に働いていたときとは場所が変わっていましたけど、知っている顔がいっぱいいて、最初は懐かしい気持ちでした。技術スタック的にもそれまでやってきたことで問題なく働けたし、子育てしている方も多かったので、その辺りの理解もあった。出社でもリモートでもOKという柔軟さもあって、すごく働きやすかったです。
でも、半年ちょっと働いて、最初のフィードバックを受けたときに違和感があったんですよね。
というと?
自分としては、技術力も大事だけど、チームで働くとか、チームで動くといったことが好きなんです。だからチームビルドなどにも力を入れたいと常々思っていて。そういった部分の啓発を、すごく進んでというわけではないですけど、それとなくみんなにお勧めする感じの立ち位置をとっていました。自分としては、そうやって楽しく働いていたつもりだったんです。
でも、その最初のフィードバックで「にしはらさんに期待していることとはちょっと違うかも」と言われてしまって。それがすごくショックだったんですよね。間接的に「エンジニアなんだから、もっとコードを書け」と言われているような感じがして。そうだったのかーと思って、そこからはしょぼんとしてしまいました。
もちろん、コードを書くには書くんですけど。自分としては、チームで動いてスクラムとかをやるのであれば、チームワークとかチームビルドとか、そういうところもちゃんとやりたい気持ちがやはりあって。そういうモヤモヤをずっと抱えながら働いていました。
それで、また私の悪い癖なんですけど、SNSで「うーん」みたいな気持ちを漏らしてしまって。もちろん知り合いにも筒抜けだから、すごくオブラートに包んだ上で、ですけど。そうしたら以前連絡をとっていたSmartHRの人事の方から連絡が来て、良かったらまたお話ししませんか、って。


よく見ているものですね。
そう、よく見ているんですよー。本当にすごいなと思う。でも、そういう気持ちになっていた矢先だったので、まずは話を聞いてみようと思って会いに行きました。
その「チームで働く」ことを重視する志向はどこで生まれたものなんですか?SESにいたときはそこまでチームっていう意識でもないですよね?
ああ、そうですね。もちろんチームにはいるんですけど、実質的には一人でやっているような感覚でした。チームで動くみたいなことを初めて実体験したのは、やっぱりくまポンに入ってからだと思います。
最初は、チーム内で毎回ミーティングをしてとか、期待値調整してとか、「面倒臭いなー」「もっとやりたいようにやればいいのに」とか思っていたんですけど。でも、やっていくうちに、いい感じに手分けして作れると、一人では生み出せないものができることを実感できて。相談し合えるし、やり遂げたときにみんなで喜びを分かち合えることのよさもすごく感じましたし。チームで開発するってすごく楽しいんだなっていうのをそこで知りました。
では、楽しくチームで働くことを求めて辿り着いたのがSmartHRだった?
そうです。転職するときに「知り合いがいる」「働きやすそう」という見込みだけで決めてしまった反省があり、次は同じ失敗を繰り返してはいけないと思っていました。だから人事の方からお話をいただいた際も、自分が理想とする働き方とか、チームのあり方とか、こういう悩みがあるから今転職を考えているのだといったことを包み隠さず、すべてお話しして。そうしたら「話すだけだと会社のカルチャーはわからないと思うので、体験入社してみませんか」と言っていただけて。
今はやっていないんですけど、当時のSmartHRには体験入社の制度があったので、スクラムイベントの日と開発の日を一日ずつ、体験させてもらいました。
体験してみて何がわかったんですか?
SmartHRに対しては勝手にキラキラしたイメージを持っていたんですけど、実際にチームに入ってみると、当たり前ですけど開発自体はごく普通というか、地道に開発していることがわかって。働いている人たちはみんな優しいし、コミュニケーションが取りにくいと感じる人もいなくて、開発しやすそうな雰囲気が感じ取れました。
スクラムイベントの日には、当時50人くらいいた開発メンバーがほぼ全員集まって、付箋を出したり、KPTをやったりするんですけど、ちょっとした冗談を言いながらやっていて、すごく雰囲気がいいし、その上で言いたいことを言い合っている。いい意味で真面目すぎないのもいいと思いました。それこそくまポンのころを思い出すくらい、ちゃんとコミュニケーションをとって仕事をしている人たちというのが伝わってきました。
病という青天の霹靂
乳がんの闘病生活のお話も、お聞きできる範囲でぜひ伺いたいと思っていて。発覚前には何か不調を感じていたんでしょうか?
それが予兆はまったくなくて。本当に変わらぬ日常を過ごしていたんです。見つかったのは、SmartHR入社2年目の会社の健康診断で。それまでマンモグラフィーを受けたことが一度もなくて、無料で受けられたので、試しに受けてみようかな、と。そうしたら見つかった。だからびっくりしました。
結果を受け取りに受付へ行ったら「先生からお話があるようなので、残ってもらっていいですか」と言われて。「その場では正確な診断ができないので、専門の病院で検査するように」と案内されました。その場で紹介状を書いてもらって、予約の電話も入れてもらって。


宣告されたときのお気持ちというのは……
その時点ではまだ確定したわけではないし、案外軽い気持ちで受け止めていました。口の下にピアスを開けたばかりだったので、手術をして塞がっちゃったらいやだな、とか。呑気に考えていましたね。
でも、その後組織検査をしたところ、やはり乳がんだとわかって。乳がんにもいろいろと種類があって、本当に切除するだけでいい場合もあるし、抗がん剤治療を必要とするケースもあるんですけど、どういった種類かがわかるまでにはまた2週間くらいかかると言われました。
「ああ、乳がんなんだ」「一番重くないのがいいな」と祈りながら2週間待って、結果を聞きに行ったら、フルコースじゃないと無理みたいな感じで。抗がん剤治療もするし、放射線治療も、手術もする。世間の人が「がん治療」と聞いて思いつくものを全部やらなければいけない乳がんでした。
でも、人間ってびっくりしすぎるとよくわからなくなるものみたいで。先生の言葉を一気に浴びたせいで、全然現実味がなかった。仕事しながら治療している人もいるし、まあ行けるんじゃないかくらいの軽い気持ちだったと思います。
当然、お仕事は休むことになる?
発見が早く、そこまで進んでいるわけでもなかったので、がんのせいでどうこうなるということはなかったんですけど。抗がん剤には3種類あって、最初の1本目がすごく強い薬なんですよ。髪の毛が抜けるのもそれ。白血球の数も一気に減ってしまって、血中に酸素がなかなか送れなくなる。その分、疲れやすくなったり、吐き気がして気持ちが悪くなったりするんです。
打ったそのときは意外に大丈夫と思ったんですけど、直後に廊下で倒れて、その後はずっと風邪を引いたときのようにだるい状態が続いて。仕事をしようと思ってもまったく集中できないし、人の話も耳に入ってこない。これは無理かもしれないと思って、先生に診断書を書いてもらって、会社に相談して休ませてもらうことにしました。
治療が進むにつれて、その状況が変わっていった?
一番強い抗がん剤治療が終わったあとは、割と元気になりました。最初は手術をするまで半年くらい休職する予定だったんですけど、一番強い薬の期間が終わると、体力はないんですけど、気持ち悪くて仕事ができないといったほどではなくなったので。
でも、ちょっと元気になるといろいろと考える余裕が出てきて、「このまま休んでいて、今後のキャリアはどうなってしまうんだろう」とか、またぐるぐる考えてしまうんですよね。休んで時間がある分、なおさら。で、そんなことを考えてるくらいなら早めに復職しようと思って、先生と会社に相談して、復職時期を半年繰り上げてもらいました。そこからは治療をしながら働くことにして、抗がん剤の日だけはお休みをもらって、それ以外の日は働いていました。
病気を経験したことで人生観や仕事観などに変化はありましたか?
多分みんな同じことを言うと思うんですけど、まさか自分が病気になるなんて思っていなかったので。なるときは突然なるものなんだな、というのを実感しました。自分はたまたま発見が早かったから元気だけれど、もしあのとき発見されなかったらどうなっていたか。今元気に働けていたり、普通に生活ができていたりするのは、本当にたくさんの偶然が重なってできていることなのだと改めて思いました。
それからは、やりたいと思ったらすぐにやらないとダメだと思うようになりましたね。これまで、「小さい躊躇」をたくさんしていた気がするんです。この勉強会は子どももいるし今度でもいいかなというような。でも、明日もあるとか来年もあるとか思っていたら、その明日はやってこないかもしれない。もともとダメもと精神で動くタイプではあったんですが、それからはより一層、そういうことを考えるようになりました。
そのことがCREの活動にもつながっていく?
カスタマーサクセスとか顧客信頼みたいなことをやりたいというのは、それ以前からずっと思っていたことだったんですけど。それを本腰を入れてやろうかと思ったタイミングで病気が発覚して、休職したり、思い切り自分のテンションをかけて取り組めない状況に追い込まれてしまったんです。やりたい気持ちはすごくあるのだけれど、できない期間が4年くらい続きました。
そこからだいぶ元気になり、やりたいことはやらなきゃダメだと思うようになったので、社外の人にお願いしてインタビューするなどをやり始めました。
病気をしていなくても、いずれやっていたことかもしれません。でも、病気の前は「会社を説得して部を作るなんて難しそうだな」「そういうのって苦手なんだよな」とか、言い訳しているところがあったと思うし、病気になったからこそ「どうにかして作ってやる!」という気持ちになれた気はします。


改めて、情熱を注ぐ対象としてのCRE
CREにはどういう経緯で興味を持ち始めたんですか。SmartHRには、エンジニアが持ち回りで行うユーザーサポート業務「DESK業務」があるとも伺いましたが。
DESK業務ももちろんそうなんですけど、復職してくまポンに拾ってもらったときの「お手伝い」がまさにそういう仕事だったんです。ECサイトに寄せられるテクニカルな問い合わせに、開発メンバーが答えていると手が止まってしまう。そこで、代わりに答える要員として入ったのが私でした。
自分でコードを調べて、動かしてみて、サポートの方と一緒にお客様に伝えるみたいな仕事を2年くらいしていました。うまく解決できるとお客様は喜んでくれるし、逆に怒っているお客様に直接お話を聞きにいくこともあって、それは大変ではあるんですけど、「使ってくれる人がいるってありがたい」と思えたりもして。こういう仕事にはアプリケーションを作るのとは別の楽しさがあるのを感じました。
その当時はCREという言葉も知らないし、それがキャリアとして成り立つものとも思っておらず、ただ単に楽しいなと感じていただけですけど。でも、SmartHRに入ってDESK業務をやっていると、その頃のことをやっぱり思い出すんですよね。
問い合わせの量はSmartHRの方が圧倒的に多いし、年々増えているから、課題感は今の方がずっと大きいです。かといって、それにすごくコミットできる人がいるわけでもない。ここを過去の経験も踏まえてなんとかできる人になれたらいいなというのがあって、取り組んでいる感じです。
なるほど。
CREをやってみたいと思っているというアピール自体は、1on1などの場でずっとしていたんですけど。でも、ユニットを作ることのメリットを伝えるのには難しさを感じていて、なかなか組織を納得させられずに、難航している時期が続きました。
そこに今の上長の方が入ってきてくれたことで、状況が大きく変わった気がします。彼は日本で初めてCREを立ち上げた人で、SmartHRに来た時点で「強くてNew Game」状態だったというか。それまでの失敗や経験を踏まえて、組織はどうあるべきか、CREのキャリアはどうあるべきかといったことに関して、すごくアイデアを持っていた。それを組織にちゃんとした形で提示してくれたことで、「これだったら部やユニットとしてもいけそうだ」という機運が高まったのではないかと思います。


にしはらさんは今後、CREという新しいキャリアを自ら切り拓いていきたいと考えているわけですか?
エンジニアとして、こういう形でもキャリアが積めるんだという、先駆者ではないですけど、ロールモデルを仲間と一緒に作っていけたらいいなと思っています。
スペシャリストやフルスタックなど、エンジニアのキャリアにはいろいろな道がありますが。
自分は情報系の学校を出ているわけではないし、技術にめちゃくちゃ強いわけでもないので。周りにいるすごい人たちを見ていると、同じ土俵で戦うのは無理ではないかという気持ちにやっぱりさせられます。
であれば、自分は自分の強みを活かした戦い方をしたいと思う。エンジニアという仕事が好きで、手を動かすことをずっと続けていきたいというのももちろんありますけど、一方で人とコミュニケーションをとることが好きだし、できる方でもあると思うので。そこを活かした新しい形を作ることができたら、自分はその道でキャリアを掴めるのではないか、と。どうにかうまくいくところはないかというのは、ずっと思っていたことでした。
そんなときに、技術的な困りごとを解決する、お客様からの信頼周りをエンジニアリングでサポートしていく、CREという職種があるということを知ったんです。それは自分のやりたいこととマッチしていて、すごくしっくりくる。もしかしたら自分が求めていたのはここなのかもしれないという気持ちになりました。今はそこに一筋の光を見出している感じです。
でも結局は気持ちの問題?
過去の選択の失敗から学び、次の選択の機会に活かすというお話が何回か出てきました。あえて聞いてみたいのですが、「失敗」というからには、仮にもう一度やり直せるとしたら別の選択をしていたという感覚があるのでしょうか?
「あのときこうしておけばよかった」という思いは確かにたくさんありますよ。でも「人生でやり直したいところはどこですか?」と聞かれたら、自分の中ではあまりないなって。なぜって、やり直すと今がなくなってしまうから。これまでの一個一個の間違った選択も、そこで間違ったからこそ、今につながっているわけで。本当にそうしてしまっていたら、絶対に今はないわけですよね。
とてもよくわかりますが、いい・悪いがないとなると、詰まるところ「選択」なんてなんだっていいってことにはならないですか?
そうなんですよねえ。だから最近は「結局のところ、自分の気の持ちようなのかな」と思っているところもあって。自分が気落ちしているときには最悪に思えたことでも、自分が元気に、楽しく、「明日はないかもしれないから全力で生きる!」となってからは、楽しく捉えられているような気もするから。
病気を経て、いろいろなものに参加したり、ポジティブに動いたりするようになってから、エンジニアとしてのキャリアもだいぶポジティブに進んでいる印象があるんです。「エンジニアとしてこうなりたい!」「だからこう動こう!」みたいな強い気持ちに従って動いているわけではないんですけど、自分が楽しくやる、全力でやると思って行動するようになったら、エンジニア人生がいつの間にかポジティブなものになってきているなあって。
そうなんですね。
それこそ立ち上げたかったユニットが立ち上がったりもしたし、任されることが増えて、技術的な新しい情報が自然と入ってくるようにもなったし。人とのつながりも新しく生まれて、組織を超えた新しい動きにもつながっている。改めて振り返ると、そのように感じるんです。
悩んでいる人からしたら「そんなふうになんて考えられないよ!」と言われてしまうかもしれないですけど。すごくベタですが、結局「気持ち!」みたいなところはあるのかなって。何周も回って、最近はそこに落ち着いている気がします。


